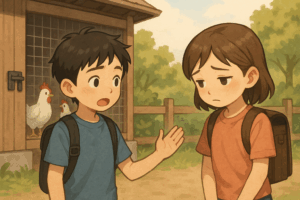むかしむかし、山の奥にある小さな村に、源さんという年老いた郵便配達員が住んでいました。源さんは若いころから村々を歩き、どんな天気でも手紙を届け続けてきた人です。足が痛くても、雪が積もっていても、手紙を運ぶ姿はまるで風のように静かで、あたたかく、村の人々は彼を「歩く手紙」と呼んで親しんでいました。
ある日、源さんはいつものように配達の準備をしていると、郵便袋の中に不思議な封筒が一枚紛れていることに気づきました。宛名も差出人も書かれていないその封筒には、ただ一言「ありがとう」とだけ記されていました。誰宛でもないその手紙に首をかしげながらも、源さんは何か胸に引っかかるものを感じ、そのまま山の中腹にある古い神社へと足を運びました。そこはかつて村人たちがよく集まった場所で、いまでは訪れる人も少なくなった静かな場所でした。
源さんはその手紙を賽銭箱の横にそっと置き、手を合わせて言いました。「誰に届くかわからんが、こういう手紙も悪くないなぁ」。それから数日後、村の若者が源さんを訪ねてきました。彼は緊張した面持ちで言いました。「あの、神社に置いた手紙……あれ、自分が書いたんです」。若者は、進学のために村を離れていたが、村での思い出や支えてくれた人たちへの感謝がこみあげ、でも誰にどう伝えればいいのかわからず、匿名の手紙を書いて神社に置いたというのです。
源さんはゆっくりと頷きました。「なるほどなあ。でも、届いとるぞ、その気持ちは」。若者は目を丸くして、「ほんとうに?」と尋ねました。源さんは言いました。「言葉は時に形がなくても、ちゃんと人の胸に届くもんや」。それから若者は安心したように深く頭を下げ、「また書いてもいいですか?」と笑いました。
それから村では、匿名で感謝や想いをつづる手紙を書く人が増えていきました。手紙は神社にそっと置かれ、だれにも読まれず、けれどだれかの心を温めるものとして扱われました。読まれることを目的としないその手紙は、まるで心の中に置くろうそくのように、静かに灯をともす役目を果たしていたのです。
ある年の秋、源さんは静かに息を引き取りました。その知らせを聞いた人たちは、思い思いの言葉を綴った手紙を持ち、山の神社に集まりました。「あなたに届けたかった」「ありがとう」「またいつか」と、さまざまな想いの言葉が、神社の境内を静かに満たしました。
その日の夜、空には一筋の流れ星が走り、村の子どもたちは「あれ、源さんだ」と声をあげました。それ以来、神社のあたりには夜な夜な小さな灯が見えることがあり、「あの世から源さんが手紙を集めに来てるんだ」と語られるようになりました。
いまでもその村では、「見えない手紙」を書く風習が残っています。届くかわからない手紙を、それでも書いてみる。言葉が、だれかの心に届く奇跡を信じて。源さんの足音が聞こえなくなったあとも、村には今も変わらず、やさしい手紙の気配が流れているのです。そしてそれは、新しい世代にも静かに受け継がれていく、小さな文化となって村を包んでいます。
一言解説
手紙を通じて匿名でも感謝を伝える心のつながりを描く物語です。届くかどうかわからない手紙が、人と人をやさしくつなぎます。
考えてみよう
- 源さんはなぜ心を揺さぶられたのかな?
- 名前を書かずに手紙を出す意味は何だろう?
- あなたなら誰に「ありがとう」を伝えたい?